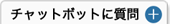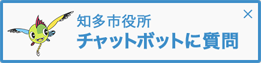令和6年度
日本赤十字社愛知県支部連携事業(キャリア教育支援)
令和7年3月13日、日本赤十字社愛知県支部、名古屋グランパスと連携し、キャリア教育支援事業を実施しました。
名古屋グランパスでポルトガル語の通訳の仕事をしている佐々木トニーユタカ氏による通訳の仕事についての講話を通じて、子どもたちが様々な職業の社会的役割や自己の生き方について考える機会となりました。
また、通訳という職業を紹介するとともに、自身のルーツや現在の活躍に繋がるまでの苦労や挫折などのエピソードを聞くことができました。
馴染みのあるスポーツチームに関わる仕事に、つつじが丘小学校の6年生(54名のうち15名は外国にルーツを持つ児童)は興味深々で話を聞いていました。
話を聞いた児童からは、「何よりも諦めないことが重要だと学んだ」「誰かの役に立てる職業を目指したい」という感想がありました。


つつじが丘小学校6年生の児童との集合写真 児童が講師に質問する様子
多言語生活オリエンテーション
市内の外国人市民に、日本での日常生活を送るのに役立つルールや情報を直接多言語で提供し、地域社会への理解を促進することを目的に、令和7年1月26日に、つつじが丘コミュニティセンターで、多言語生活オリエンテーションを実施しました。
前半は、「日本での学校生活」について、市民活動団体のちたビジョンプロジェクトが、「就学援助」について、市役所学校教育課が講座を行いました。
ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、中国語の同時通訳をし、日本語がわからない参加者にも講座を聞いてもらうことができました。
講座のテーマは、外国人市民が困っていることや、新しい制度などニーズを把握して決めています。
後半は、市民の方から無償でいただいた学用品を参加者に無償で提供する譲渡会を行いました。
今回は、6か国、42名の方に参加していただきました。
また、多文化共生に興味のある6名の方にサポーターとして事業に携わっていただきました。


講座の様子


講座の様子 託児スペースの様子


市民の方からいただいた学用品
日本語ボランティア養成講座
外国人市民のための日本語教室における日本語学習の指導者の新規獲得と育成を目的に、市民活動センターで全3回(9月29日、10月6日、10月13日)講座を実施しました。
講師に矢島 清香さん(公益財団法人名古屋YWCA)を迎え、延べ77名の方に参加していただきました。
参加者から 「自分のできる範囲で地域の方や市の取組みに参加したい」「外国人市民に対して勝手なイメージを持っていたことに気づけた」「日本語教室の活動を実際に見学したい」「外国人市民の視点で問題を考え、寄り添う大切さを学べる良い機会だった」など様々な感想をいただきました。


講座の様子 トランプを使った多文化共生を学ぶゲーム
行政職員向けのやさしい日本語研修
市役所へ来庁する外国籍市民が増えている中で、職員が外国籍市民に寄り添い、適切な対応ができることを目的に、令和6年8月15日に、行政職員を対象としたやさしい日本語研修を実施しました。
名古屋港出入国在留管理局在留支援部門の方を講師に招き、やさしい日本語に言い換える、書き換えるポイントを学びました。
「やさしい日本語」とは、普段使われている日本語を外国人にもわかるように配慮した、簡単な日本語のことで、常に決まった一つの正解があるわけではありません。やさしい日本語を活用することで、翻訳・通訳が不要となり、効率よく情報を伝えることができます。
わかりやすい、平易な言葉遣いや表現は、外国籍の方だけでなく、子どもやお年寄り、障がいを持つ方にとっても有効とされる、これからの社会に必要な共通言語です。
(やさしい日本語への置き換えの例)
・高台に避難してください → 高(たか)いところに 逃(に)げてください
・土足厳禁 → 靴(くつ)を 脱(ぬ)いでください
・公共交通機関でお越しください → 電車(でんしゃ)や バスで 来(き)てください
出前講座(佐布里小学校)
令和6年6月21日に、佐布里小学校の6年生を対象に、多文化共生について出前講座を実施しました。
自分自身の好きなものや得意なことや価値観が、隣にいる友達や近所に住んでいる人と違っていることを知り、自分の「当たり前」が他の人の「当たり前」とは違うことを学びました。
また、学校や地域で、多言語で表記されているものや、ふりがながついている看板など、多文化共生の取組みを紹介しました。
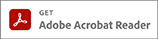
- PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。