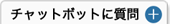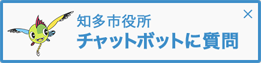更新日 2025年02月18日
家庭から出る燃えるごみのなかに多く含まれる生ごみは、その約8割が水分で、重さがあるだけでなく、そのまま燃やすと、ごみの燃焼効率にも悪影響が出ます。食品を使い切る、食べ残しを減らす、水切りをするなど、生ごみの減量を進めることで、家庭から出る燃えるごみが減ることはもちろん、燃焼効率の向上によるCO2削減や、ごみ処理費用の削減にもつながるなど、多くのメリットがあります。
そこで今回は、生ごみの減量に役立つ知識のひとつとして、生ごみ処理器「キエーロ」をご紹介します。
生ごみ処理器「キエーロ」とは…
キエーロとは、土の中にいる微生物の力を利用して生ごみを分解して消滅させる、比較的お手軽な生ごみ処理容器です。
 |
 |
 |
・土の中にいる微生物が分解できるものなら、食用油や汁物の残りなども含め、ほとんどの生ごみを投入できます。
・水分を必要とするので、生ごみの水切りが不要です。
・生ごみは分解されて消え、土の量も増えないので、維持費用がほとんど不要で、長期間使用が可能です。
・うまく使えば、土に埋めた後にほとんど臭わず、虫なども発生しにくいです。
必要なもの
| 土 |
園芸用の「黒土」が入手しやすく向いています。 砂や砂利、粘土質の土などは不向きですので、使用しないでください。 |
| 容器 |
雨水を防ぎ、日当たりや通気性を良くして、微生物の働きを助けます。 形状としては、透明な波板等のフタで日光が入り、脇に隙間を作ることで空気を取り込みやすくしています。 大きいほどたくさんの生ごみを埋めることができますが、その分、邪魔にならない置き場所が必要です。 キエーロの置き場所は、風通しや日当たりの良い場所(庭やベランダなど)がおすすめです。 |
※その他あった方がよいもの
スコップ、ジョウロ、一時的に生ごみを貯めておくための密閉容器など。
キエーロの使い方
|
1.土に穴を掘る
|
15~20cmほど穴を掘ります。掘った土は、後でかぶせるために、脇によけておきます。 穴を複数掘れる大きさの容器なら、次に生ごみを埋める場所も意識して掘ると効率的です。 |
|
2.生ごみと水を入れる
|
水分が微生物の働きを助けます。穴の中の土が湿って、握ったら少し固まる程度の水を入れます。 生ごみの水分量が十分ある場合は、水の量を減らして調整します。 |
|
3.土とよくかき混ぜる
|
穴の中で、土とよく混ぜ合わせ、なるべくたくさん土が生ごみに触れるようにします。 空気もよく含むように、柔らかく混ぜこみましょう。 |
|
4.乾いた土で埋める
|
最初に掘ったときに出た土を、乾いた状態のまま、かぶせて埋めます。 かぶせた土が湿っていたり、埋め方が浅いと、臭いや虫の発生原因となります。 分解にかかる時間は、夏季は概ね1週間程度、冬季は2週間程度かかります。 分解を待ちながら、埋める場所を変えて繰り返し使用することができます。 |
注意点
・微生物の力で分解するため、気温が暖かいと微生物の活動が活発になり分解が早いですが、寒くなると分解が遅くなる傾向があります。
・微生物が苦手とするものは分解しにくかったり、分解されないことがあります。大まかな目安としては、人間が食べられない物は分解しにくいので、入れることを避けた方が良いです。(卵の殻、貝殻、動物の骨、果物の種など)
よくある質問と対応について
| 虫が発生した | 生ごみが土から露出していたり、かぶせた土が湿っていたりすると発生しやすいです。しっかりと乾いた土で、深めに埋めましょう。虫の存在で、キエーロの機能に悪影響はほぼ出ないと思いますが、駆除する場合は、熱湯をかけたり、殺虫剤を使用しても大丈夫です。黒土の中にいる微生物に影響はありません。 |
| 土の表面にカビが生えた | 生ごみを処理していく過程で発生する菌種があります。微生物が働いている証拠でもありますので、おそらく問題ありません。 |
| 生ごみがうまく分解されない | 使い始めてすぐや、寒い時などは、微生物の活動が鈍いことがあります。分解の途中でも、次の生ごみを入れることは可能ですので、様子を見ながら使用してください。分解が早くなる工夫として、生ごみをなるべく細かくしてから埋めたり、2~3日生ごみをためて少し発酵させてから埋めたりすると、分解が早まります。他にも、生ごみを入れる際に、米ぬかや、使用済みの食用油を少し混ぜると、微生物が活性化され、分解しやすくなります。 |
| コロコロと土の塊が出てきた | 土の表面に現れる土の塊は、生ごみが分解されて変化したものです。悪いものではありませんが、キエーロを使いやすくしておくために、見かけたら崩しておくとよいです。 |
モニター事業についてご紹介(令和6年度実施)
50名の市民の方にモニターとして、令和6年6月下旬から12月31日までの約半年間、キエーロを実際に使用して記録をつけていただきました。アンケートも実施し、それらの報告をまとめたものを掲載していますので、ぜひご覧ください。
中間報告まとめ(令和6年6月下旬~9月30日)[PDF形式:899KB]
最終報告まとめ(令和6年10月1日~12月31日)[PDF形式:940KB]
その他
キエーロの容器について、現時点では、市販されているものを購入するか、材料を購入して自作していただく必要がありますが、お手軽な入手方法や費用の補助施策などを現在検討中です。なるべく多くのご家庭で活用していただけるよう周知・啓発に努めていきたいと思いますので、生ごみの減量に、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用下さい。