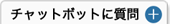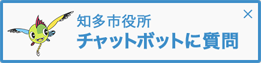更新日 2022年06月10日

ばんざい? まんざい?
万歳とは、お正月に家々を回って、家内の健康や繁栄を願う日本古来の招福芸のことだが、多くの人は「万歳」という文字を見ると、「バンザイ\(^o^)/」と読み、「まんざい」と聞くと「漫才」を思い浮かべるのではないだろうか。 しかしこれは間違いではない。なぜなら、「ばんざい(万歳)」は、もともと家が末永く栄えることを指す言葉で、尾張万歳も家の繁栄を願って行う慶事の芸能のことだから。
また、「漫才」とは昭和8年に吉本興業が「万歳」を「漫才」に変えてネーミングしたもので、もともと上方漫才は尾張万歳がルーツだからである。
三河万歳と尾張万歳
愛知には、“尾張万歳”と“三河万歳”が今も残っているが、その違いについて、尾張万歳家元・五代目長福太夫(ちょうふくだゆう) 北川幸太郎(きたがわこうたろう)さんは、こう語る。「三河万歳のほうが神道に基づき、基本2名で格式高く行うのに対して、尾張万歳は、大勢で演じるにぎやかで庶民的な芸能。徳川家の保護があった時代は、家康が三河の出身だから、三河万歳を贔屓(ひいき)にしていましたが、時代が変わると、面白いほうに人気が集まり、お堅いほうが衰退し始めたんです」。
しかし、尾張万歳師は三河万歳の危機を放っておけなかった。仕事のなくなった三河万歳師に自分たちの芸を教えて、同じように万歳興行を行うように指南したのだ。窮した人に手を差し伸べる、心優しい知多人の一端がここにある。


日本のお笑いのルーツ!
こうして正月の風物詩となった尾張万歳は、芝居仕立ての“三曲(さんきょく)万歳”や上方漫才のルーツとなった“門付(かどつけ)万歳”など興行的に発展していき、ブームに火がついた。北川さんによると、関西から多くの芸人が北川家へ尾張万歳を学びにやって来て、「ボケとツッコミ」という漫才のスタイルを確立したというからすごい。(尾張万歳は、扇子を持って祝詞を唱える太夫(たゆう)がボケ役、鼓をたたいて合いの手を入れる才蔵(さいぞう)がツッコミ役) 日本のお笑いの原点がここ、知多市にあるとはとても誇らしい。
この尾張万歳、平成8年には国の重要無形民俗文化財の指定を受けている。
男子高校生も参戦
さて、「御殿万歳」を見せてもらえるというので、尾張万歳保存会の稽古場である知多市青少年会館へ。トランクを手にして現れたのは、にこやかな笑顔にも貫禄を感じるベテラン勢だ。その中に、…10代の男の子がいる!?
聞けば彼は、愛知県立知多翔洋高等学校の3年生で、尾張万歳の授業に感銘を受け、この日から保存会に入会するという。「万歳の動きや掛け合いが好き。そんな大そうなことじゃないけど、伝統をつなげていきたいと思って」とはにかんだ笑顔を浮かべる。若い世代もとりこにする尾張万歳とは、一体どんなものなのか。


めでたい笑いが詰まった「御殿万歳」
そして始まったのは「御殿万歳」。「鶴は千年、亀は万年の~お祝い申す」と中央の太夫さんが厳かに吟じ始める。
まず一本の柱が一宮
真澄(ますみ)高尾(たかお)の大明神ヨ
二本の柱が二の宮神社
三本の柱が榊(さかき)の神社
四本の柱が弁財天ヨ
五本の柱が津島の神社…(以後続く)
前半は柱1本ごとに各地の神様を呼び込んで、御殿を作るという場面。我が家の柱に、熊野神社や熱田神宮などの名だたる神社や神様が居て、家を守ってくれている。正月の飾り物を並べて、門を開いたら、七福神が家の中に舞い込んできた…という唄だ。目の前には、風変わりな神様がガヤガヤと集う、めでたい正月の風景が広がっていく。
テンポよい掛け合いが楽しい後半に注目!
ここからが、さらに楽しいところ。粛々としていた雰囲気が一転、後半には太夫も才蔵も立ち上がり、テンポのいい唄が始まる。「誰じゃどなたじゃ」と太夫が言えば「ほててこてんの布袋様ではないか」とほおを膨らませて、大きなおなかを両手で抱える才蔵。七福神の姿を思い浮かべながら、思わず笑いが出てしまう。ユーモラスな動きと「すととことん」「ぐんにゃりすんにゃり」などのセリフ(詞章)の面白さに、終わるころにはこのフレーズが頭の中で延々とループしてしまったほどだ。


若手もクセになる笑い芸
それにしても、尾張万歳は稽古ですら笑顔が絶えない。心から演じるのを楽しんでいる様子に、つられて笑みがこぼれてくる。「皆さんに笑いを届けて、幸せになっていただくのが招福芸ですから」と北川さん。保存会の練習には、小学生向けの市の講座から入った若者、親子で始めた人や名古屋から通っている女性など、その魅力に取り付かれた若い世代が集まる。伝統芸だから、と構えていたが、みんな本当に楽しそうに演じている。
知多人の幸せを運ぶ尾張万歳を見に行こう
地元では八幡(はちまん)神社の元旦奉納公演、3月の佐布里池梅まつり、県外では多賀大社の御田植祭り(滋賀県)など、多くのイベントに登場する。
見たことのない方は、地元の誇り・尾張万歳を、ぜひ生で見てほしい。「えへ♪ おほ♪」が頭から離れず、陽気に過ごせること請け合いだ。
取材日:平成28年12月

尾張万歳フォトギャラリー