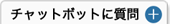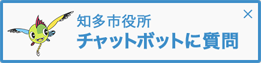更新日 2025年12月12日
申請書類をホームページ上でダウンロードいただけるようになりました。申請にあたりまして、事前にホームページ上のご案内や注意事項をよくご確認いただき、ご不明な点がございましたら、健康推進課までお問い合わせいただきますようお願いします。
不妊治療費補助について
市では、少子化対策として、妊娠を望んでいる夫婦に経済的な負担の軽減をはかり、適切な医療が受けられることを目的として、不妊治療費の補助を行っています。
補助制度の概要
対象者
次のいずれにも該当する方
- 夫婦(事実婚関係含む)のいずれか一方又は両方が、市内に住所を有していること
- 医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと
- 妻の年齢が43歳未満であること。(ただし、治療中に妻の年齢が43歳に到達した場合は対象。)
補助対象医療行為
産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において受けた一般不妊治療及び特定不妊治療(検査を含む)
ただし、次の不妊治療を除きます。
- 保険適用外の治療等
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
補助額
補助対象経費の2分の1とし、1年度につき上限20万円
補助対象経費
不妊治療に要した医療費のうち、健康保険適用分の自己負担額
※ただし、高額療養費制度や付加給付金等、当該医療費に対する他の法令や各健康保険独自の取組等による給付がある場合は、その額を控除します。
※文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の治療に直接関係の無い費用は除きます。
※他自治体で補助を受けた治療分は補助対象経費から除きます。
高額療養費制度について
医療費の家計負担が重くならないよう、1か所の医療機関で受けた医療のうち、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページへ)(新しいウインドウで開きます)
※限度額適用認定証を事前に入手し、医療機関等の窓口で提示すれば、窓口での費用負担が上限額までになり、高額療養費の申請が不要になります。特に、特定不妊治療(体外受精や顕微授精などの生殖補助医療)を受ける場合、治療費が高額になると見込まれるため、治療前に認定証を入手されることをおすすめします。
限度額適用認定証について
ご加入の保険組合等から交付される「限度額適用認定証」を医療機関等の窓口で提示していただくと、窓口での負担が外来・入院ともに上限額までとなります。(上限額は年齢・所得に応じて定められています。)「限度額適用認定証」を提示せずに医療費を支払うと、後日、高額療養費の申請をご加入の保険組合等へ申請いただいた後、ご加入の保険組合から交付された高額療養費の支給決定通知書の市への提出が必要となります。通常、診療月から4か月程度かかりますので、不妊治療費助成金の支払いも遅れます。「限度額適用認定証」については、治療前に、加入している保険組合等にお問い合わせください。
※ひと月の支払いが57,600円以上で、補助金申請時に限度額適用認定証の提示がない場合、加入されている健康保険組合等の保険者に高額療養費等の支給の有無を確認することがあります。高額療養費等の制度に該当していた場合は、その額を控除させていただきます。
付加給付金について
保険組合において独自に決められた上限額を超過した費用が支給される制度です。制度の有無を含め、詳しくは加入している保険組合等にお問い合わせ下さい。
申請方法
交付申請の時期
| 補助対象期間 | 提出期日 | |
|---|---|---|
| 令和7年度分 | 令和7年3月1日から令和8年2月28日まで | 令和8年3月13日(金)まで |
※領収書等の発行に期間を要する場合などにより提出期日に間に合わない場合でも最終診療日から1年以内であれば申請を受け付けますが、事前に健康推進課までご連絡をいただき、提出書類が揃い次第、速やかに申請してください。
申請書類
健康推進課(保健センター内)に以下の書類を提出してください。
申請書の受付は必要書類すべてが整った時点とします。
※高額療養費制度・付加給付金の支給の有無につきましては、事前に保険組合等にお問い合わせください。申請書類確認時に支給を受けていることが確認できた場合は、支給額・明細書類を準備いただき、必要書類がすべて整った上で申請受付となります。なお、支給を受けたことが申請時以降に確認できた場合、補助金の返還を求めることがあります。
申請書類一式は健康推進課窓口でも配布しています。
| 提出書類 | 記入例など | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 必ず必要な書類 | 1 | 交付申請書兼実績報告書(記入例)[PDF形式:240KB] | ||
| 2 | 同意書兼申告書(記入例)[PDF形式:220KB] | |||
| 3 | ー |
医療機関に記入を依頼し、証明を受けてください。医療機関が証明書を発行するのに時間がかかります。※複数の医療機関を受診されている場合は、医療機関ごとに証明書の記入を依頼してください。 |
||
| 4 |
申請しようとする治療に係る領収書 |
ー | 医療機関が記入する補助事業等受診等証明書に記載がない領収書は助成対象外です。原本の場合、こちらでコピーし、返却します。 | |
| 5 | 医療保険情報が確認できる書類等(夫婦とも、事実婚の場合は両人とも) | ー | (例)資格確認書、マイナポータルの保険情報がわかる画面の写し等 | |
| 6 | 振込先の口座番号が確認できるもの | ー |
通帳、キャッシュカード等(コピー可)※ゆうちょ銀行の場合は通帳をお持ちください。 |
|
|
条件付きで必要な書類 |
7 | 事実婚関係に関する申立書[Word形式:19.5KB] | ー | 事実婚関係の方のみ提出が必要となります。 |
| 8 | 戸籍謄本 | ー |
住民基本台帳で夫婦の婚姻関係が確認できない場合や夫婦の一方が知多市外に住民票がある場合。 なお、事実婚関係の方は両人の戸籍謄本が必要です。 |
|
| 9 | 高額療養費制度、付加給付金等の支給額、明細が分かる書類(コピー可) | ー |
高額療養費・付加給付金が支給された方の場合のみ。なお、支給があった月に、不妊治療以外で病院に行った場合はその領収書を持ってきてください。明細が分かる書類がない場合は保険組合に問い合わせて発行してください。 |
|
補助金の交付
申請書類を審査後、指定の金融機関口座に補助金をお振込みします。(1か月程度を目安)
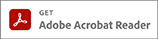
- PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。