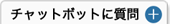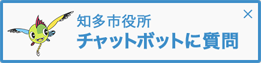更新日 2025年09月17日
市の財政の健全度を表す健全化判断比率の4指標と公営企業の健全度を表す資金不足比率を公表します。
令和6年度決算に係る健全化判断比率と資金不足比率は次のとおりです。
健全化判断比率及び資金不足比率の状況[PDF形式:380KB]
健全化判断比率とは
| 項目 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 |
|---|---|---|---|---|
| 指標の種類 | フロー指標 | フロー指標 | フロー指標 | ストック指標 |
| 何がわかるの? | 収支尻の赤字は収入の何パーセントだったのか | 市の会計全体の収支尻の赤字は、収入の何パーセントだったのか | 収入のうちどれくらいを借金の返済に充てているのか | 背負っている負債は、収入の何年分くらいあるのか |
| 算定対象のイメージ | 一般会計等 |
|
|
|
| 健全化判断比率は何かな? | 健全化判断比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定するもので、財政の健全度がどの程度の水準であるかを表します。 健全化判断比率の4指標のうち一つでも早期健全化基準を超えると、自主的な改善努力により早期健全化を図り、また、財政再生基準を一つでも超えると、国などの関与によって確実な再生を進めることとなります。 |
|||
算定対象のイメージ図
実質赤字比率
福祉、教育などを行う一般会計等の実質収支の状況について、赤字の程度を指標化したもので、実質的な赤字が市税等の財源の規模に対してどの程度の割合になるかをみるものです。
算式:実質赤字比率 = 一般会計等の実質赤字額 ÷ 標準財政規模
連結実質赤字比率
市全体の赤字の程度を指標化したもので、全ての会計の赤字や黒字を合算し、全体としての赤字額が市税等の財源の規模に対してどの程度の割合になるかをみるものです。
算式:連結実質赤字比率 = 連結実質赤字額 ÷ 標準財政規模
連結実質赤字額
全会計の実質赤字(又は資金の不足額)が全会計の実質黒字(又は資金の剰余額)を超える場合の当該超過額
実質公債費比率
地方債(借金)の返済やこれに準じる額の大きさを指標化したもので、一般会計等が負担する地方債の元利償還金や公営企業における地方債の元利償還金に対する繰出金などを含めた実質的な公債費相当額が市税等の財源の規模に対してどの程度の割合(過去3か年平均)になるかをみるものです。
算式:{ (地方債の元利償還金+準元利償還金) -
(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) } ÷
(標準財政規模-元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
準元利償還金
次の1から5までの合計額
1.満期一括償還の地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
2.一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
3.一部事務組合等への負担金のうち、一部事務組合等が起こした地方債の償還の財源に充てられたと認められるもの
4.債務負担行為に基づく支出のうち、公債費に準ずるもの
5.一時借入金の利子
将来負担比率
一般会計等の借入金や将来支払う可能性のある負担等の現在高の程度を指標化したもので、将来の負担額が市税等の財源の規模に対してどの程度の割合になるかをみるものです。この指標は、中長期的な視点で、財政の健全性を確保するための指標と位置付けられ、一般会計等の負担すべき負債に加え、公営企業、一部事務組合や広域連合、土地開発公社など、一般会計等が負担する蓋然性の高いものを負債と捉えて算定します。
算式:{ 将来負担額 - (充当可能基金額 + 特定財源見込額 + 地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額) } ÷
(標準財政規模-元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
将来負担額
次の1から8までの合計額
1.一般会計等の地方債現在高
2.債務負担行為に基づく支出予定額
3.一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額
4.加入する一部事務組合等の地方債の元金償還に充てる負担等見込額
5.退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計等の負担見込額
6.設立した法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額の
うち当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
7.連結実質赤字額
8.加入する一部事務組合等の連結実質赤字額相当額のうち、一般会計等の負担見込額
充当可能基金額
上記1から6までの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金
資金不足比率とは
何がわかるの?
収支尻における資金の不足額が事業の規模の何パーセントだったのか
資金不足比率は何かな?
資金不足比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定するもので、公営企業の健全度がどの程度の水準であるかを表します。
資金不足比率が経営健全化基準を超えると、自主的な改善努力により早期健全化を図ることとなります。
水道など料金収入を財源として独立採算で行う公営企業の資金不足の程度を指標化したもので、資金の不足額が事業規模である料金収入の規模に対してどの程度の割合になるかをみるものです。
地方公営企業法適用企業(水道事業会計、下水道事業会計)
算式:資金の不足額 ÷ 事業の規模
資金の不足額
(流動負債 + 建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高 - 流動資産) - 解消可能資金不足額
事業の規模
営業収益の額 - 受託工事収益の額
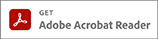
- PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。アドビシステムズ社から無料で配布されておりますので、こちらからダウンロードしてご利用ください。